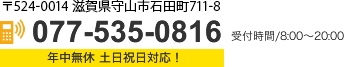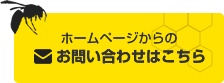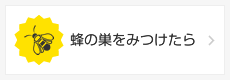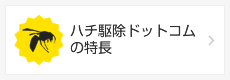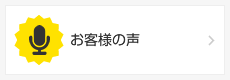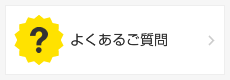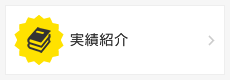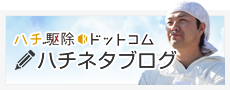ハチネタブログ
スポーツイベントで多数のスズメバチ被害
秋にはスポーツイベントを中心に様々なイベントが各地で開催されますが、この時期は、スズメバチが最も狂暴化する時期でもあります。スズメバチの巣が最大化するのと同時に、次年期の女王バチたちが誕生するため、働きバチたちには彼女たちを守ることが最大の使命になります。非常に神経質になりますので、普段よりも警戒レベルが上がり、警戒範囲も広がります。そんな時期と多くのイベントが重なるため、毎年多数のスズメバチ刺傷被害が発生してしまっています。
イベントなどで集団刺傷を引き起こすのは、ほとんどがオオスズメバチかキイロスズメバチによるものです。これらはコース脇の地中や茂みの中、橋の下などに巣を作るため、イベントの運営サイドでは事前の安全確認や点検をされていても、発見が困難なものです。万全を期すには本番と同様の音量や振動を発生させる必要がありますが、とても現実的ではありません。
近年の温暖化による熱中症のリスク増大により、運動会などの屋外でのスポーツ行事を春に開催するように変更される傾向がみられますが、これはハチ刺傷のリスク軽減にもなると考えられます。スポーツの日という祝日もありますが、いつかスポーツの秋といわれることがなくなるかもしれませんね。
スズメバチの巣駆除で高額請求…料金トラブルに注意!
8/29(火) 11:00配信 毎日新聞より
ハチの巣の駆除で高額な料金を請求される事例が相次いでいる。国民生活センターへの相談は5年間で約2・5倍に増えており、記者もとある業者に16万円超の見積もりを示された。晩夏から秋は、巣の駆除を考える人が増える時期。気を付けるポイントを専門家らに聞いた。
センターによると、2022年度に寄せられたスズメバチやネズミなどの駆除に関する相談は1437件。558件だった17年度の約2・5倍になっている。
8月上旬、記者は帰省した京都府内の実家の軒下でスズメバチの巣を見つけた。駆除してもらおうと、ネット検索で見つけた専門業者に見積もりを依頼。下見に訪れた男性は「巣の駆除で7万円、忌避剤散布が3万円、高所作業費などで6万5000円。合計で16万5000円が必要になりますね」。別の場所で巣が見つかれば、追加料金が発生するとした。
あまりに高額だったため、兵庫県西宮市にある別の業者にも見積もりを頼んだ。この業者は「巣がいくつあっても5万5000円で駆除しています」としたため、お願いすることにした。軒下だけでなく、屋根裏にも巣があることが分かり、約7時間かけて全ての巣を取り払ってくれた。
西宮市の業者によると、スズメバチは黒色のものを敵とみなして襲う傾向があるため、白色の作業着を着て、髪の毛も白いタオルで覆って作業にあたっているという。高額料金を示した業者は黒色の作業着姿だったことを伝えると「知識がない証拠ですね。今は普通のサラリーマンの男性が、小遣い稼ぎで請け負っている場合もありますからね」。
害虫駆除の専門業者らでつくる公益社団法人「日本ペストコントロール協会」で技術委員を務める村田光さんは業者選びで、担当者がスズメバチの生態を説明できるか▽費用の内訳が見積もりに記載されているか――を確認することがポイントになるという。
8~9月は、餌となるチョウなど昆虫の幼虫が減るため、スズメバチは刺激に対して敏感になり、攻撃性が増す。このため、スズメバチの巣に近付いて攻撃された人からの駆除依頼が増えるという。
協会では、地域ごとに設けている「害虫相談所」で相談を受け付けている。村田さんは「要望があれば信頼できる業者を紹介できます。相談は無料なので、気軽に利用してほしいです」と呼び掛けている。国民生活センターは料金トラブルを防ぐ方法として、複数の業者から見積もりを取ることを推奨している。【坂根真理】
このような事例や、さらに悪質なやり口での高額請求が全国で非常に多く報告されています。金額や説明が曖昧で不安を感じた場合は、しっかり踏み込んで確認することが大切で、さらに他の業者にも相談してみてください。いくつかの質問をして対応の誠実さを確認することが重要です。請求料金トラブルを防ぐために気を付けなければならない点は、おおむねこの記事に記載されている通りです。しかしながら、この記者さんが最初に見積もりを依頼した業者の16万5千円は問題外としても、次に登場する業者の5万5千円も充分高額なものに感じます。
実際に10個以上の巣が作られている住居から駆除依頼を頂くこともありますが、通常その巣の半数以上は過去に作られていた巣ですので、弊社の場合は、今現在営巣中の巣の駆除料金しか発生致しませんし、同日作業の場合は数が増えるほど割安になるように価格設定しています。高所作業車が必要になるケースでもない限り、5万円を超える駆除料金はやはり通常では考えにくい料金ではないでしょうか。
またさらに、記事中に出てくる公益社団法人「日本ペストコントロール協会」という民間の団体を通じて依頼しても、地域差はあるかと思いますが、私どもが考える相場よりも1.5倍から2倍程度高額だったと記憶しています。
高齢者ほどハチに刺されて命を落とす?真相は?
そのほとんどがスズメバチによるものですが、ミツバチやアシナガバチによるものも含まれています。

特に高齢者に多く、60歳以上が全体の約80%を占めています。
赤井英和さんの自宅2階にスズメバチの巣が!
Yahoo!JAPANニュース(Hint-Pot)
自宅2階に巨大なスズメバチの巣 赤井英和さんの妻がとった行動に「正解です」の声(8月18日 14時14分配信)より
刺されれば死に至ることもあるスズメバチ。いつの間にか自宅のベランダや軒先に巣を作り始め、気づけば巨大な塊ができていることもあります。そんな体験を、俳優の赤井英和さんの妻である佳子さんが自身のX(ツイッター)アカウント(@yomeyoshiko224)で発信し、話題になっています。巣を発見した佳子さんは、どのような行動をとったのでしょうか。
赤井佳子さん「我が家の2階に、とんでもないものを見つけてしまった」
佳子さんが驚きの報告したのは、今月12日。「どんなに小さくても、虫が怖くて怖くて仕方がない赤井がいるうちは黙っていたが、我が家の2階に、とんでもないものを見つけてしまった」とコメントするとともに、6秒の映像を投稿しました。映像には、巨大な巣を作り、そこで動き回るスズメバチが映っています。
リプライ(返信)には、「これは本職の方に依頼案件」「家にこんなんあったら想像しただけで怖い」「速攻で業者に連絡ですね」「ヤッバイですやん......」「こ、これは業者を呼ぶレベルです」「アララ 事件案件!!」などの声が寄せられました。
翌13日の投稿で佳子さんは、「昨日のスズメバチの巣ですが、みなさんのアドバイスでビビり、業者さんにお願いして、一網打尽にしていただいた。そんな、自分に危害がないときは“なんかハチがかわいそうだった”なんて少女みたいなことを言い、今日になってなくなった巣を探して戻ってくるハチには“1匹残らずやったろかコラァ”と豹変する私でした」と、専門家に駆除してもらったことを明かしました。
この駆除報告に、「さっさと撤去して正解です」「業者に頼んだんですね。それが一番です」「安心しました」「一度巣を作られると来年の巣作りの時期にはまた、やってくるかもしれないのでお気をつけくださいね」「大事に至らず、良かったです」などの声が寄せられています。
スズメバチに刺されると、アナフィラキシーショックを起こして死亡する事例もあります。刺されないようにするためには、たとえ巣を見つけても近づかないこと、刺激しないことが大切です。自分たちでなんとかしようとせず、速やかに専門家に駆除の依頼をしたほうがいいでしょう。
駆除依頼は地方自治体にも相談できます。いざというときのために、駆除の手順を確認しておきたいですね。
ニュース元
Yahoo!JAPANニュース
関連記事
Hint-Pot 2023年8月18日
このニュース記事に掲載の画像を見る限りキイロスズメバチの巣で、サイズは直径25cm前後に見えますのでハチの数は200~400匹といったところでしょうか。
巨大な巣という表現をされていますが、キイロスズメバチの巣としてはこれでも中規模のものになります。
発見と駆除があと1カ月ほど遅ければ、この巣はほぼピークの規模にまで成長していたことでしょう。
そうなれば巣の直径は40cmを超え、ハチたちの数も1000匹を超えていたと考えられます。
まだ中規模とはいえ、この巣はスズメバチのなかでも特に危険なキイロスズメバチです。
外からは見えませんが、巣の中には常に半数程度がいますし、残りの半数は次々と巣に帰ってきます。
むやみに巣に接近したり刺激するようなことをすると、中からも外からも一斉に襲い掛かられ大惨事となり、命の危険が生じます。
周囲の意見をしっかり聞き入れ、すみやかに駆除の依頼をされたのは大正解でした。
『ザ!鉄腕!DASH!!~DASH島~』に資料を提供しました
読売テレビ『ザ!鉄腕!DASH!!』番組制作会社様より資料提供のご依頼があり、協力させていただきました。
番組内の~DASH島~のコーナー内で、空になったスズメバチの巣は古くから縁起物やお守りとして飾られることがあったという内容を紹介する為に取材をうけ、その資料を提供させていただきました。
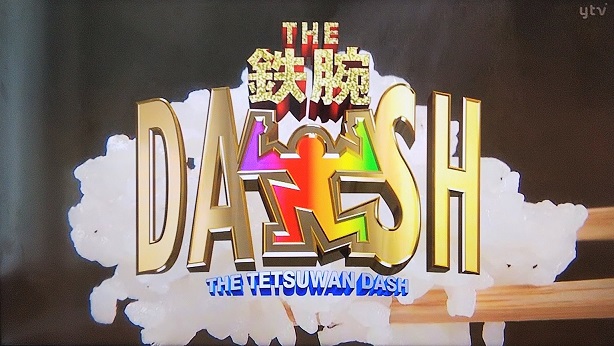 |
 |
放送日2022年11月27日(日)19:00~